遺言って、結局どれを書けばいい?──自筆と公正証書の選び方
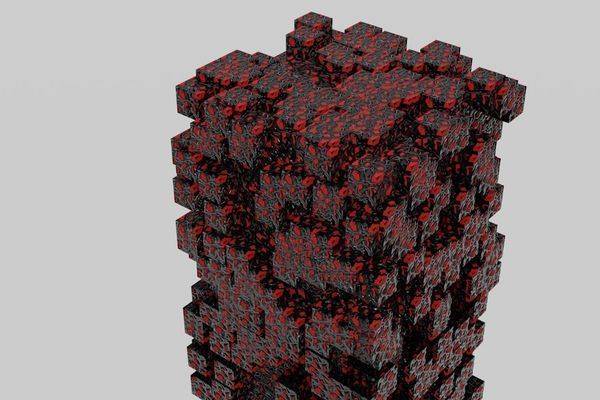
こんにちは、ライフデザインパートナーHMです。
遺言の話になると、最初の一歩で立ち止まりがちです。自分で書く自筆証書遺言か、公証人に作ってもらう公正証書遺言か。正解はひとつではありません。暮らしのサイズ、家族の距離、残したい言葉。その重なりの真ん中に“ちょうどいい形”があります。
自筆証書遺言は、思い立った日に自分の手で形にできます。法務局の保管制度を使えば、紛失や改ざんの不安もだいぶ軽くなりました。費用は抑えられますが、書き方の要件を外すと無効になってしまうリスクが残ります。公正証書遺言は、公証人と証人の目で内容と形式が整えられ、原本も公証役場で保管されます。費用はかかりますが、のちの手続きが滑らかになりやすいのが強みです。
選び方に迷うなら、まずは“どこを安心したいか”を言葉にしてみましょう。費用なのか、手間なのか、手続きの確実性なのか。大切な人へ残したいメッセージ(付言)も、どちらの方法でも添えられます。最初の一通は自筆で形にして、落ち着いたら公正証書で更新する。そんな重ね方も自然です。
少し踏み込んだ“置き方”の例も挙げておきます。配偶者が暮らし続けるための住まいの指定、未成年の子や障がいのある家族への“遺言による信託”、仲の良いきょうだいでも将来の“共有”を避ける単独名義の明示。遺言は、財産の分け方だけではなく、“暮らし方の地図”を残す紙でもあります。付言(法的効力のないメッセージ)で、思いや経緯を書き添えるだけで、受け取る側の迷いはぐっと減ります。
実務の流れは、1) 財産と受け取る人の棚卸し→ 2) 文案の作成→ 3) 自筆なら方式(全文自書・日付・署名押印・目録の扱い)を確認、公正証書なら公証役場で予約・必要書類を揃える→ 4) 保管(法務局保管/自宅金庫/公証役場)→ 5) 年に一度の見直し。家族構成の変化や住まいの売買など、ライフイベントのたびに短く見直すのが安心です。
遺言は、財産の話だけではありません。暮らし方の希望、家族への感謝、お願いごと。言葉にして残すこと自体が、誰かの心の灯になります。
※本記事は一般的な考え方の紹介です。遺言の方式・費用・必要書類は個別事情で異なります。法務局や公証役場、専門家の最新情報で確かめる前提で読んでほしいです。